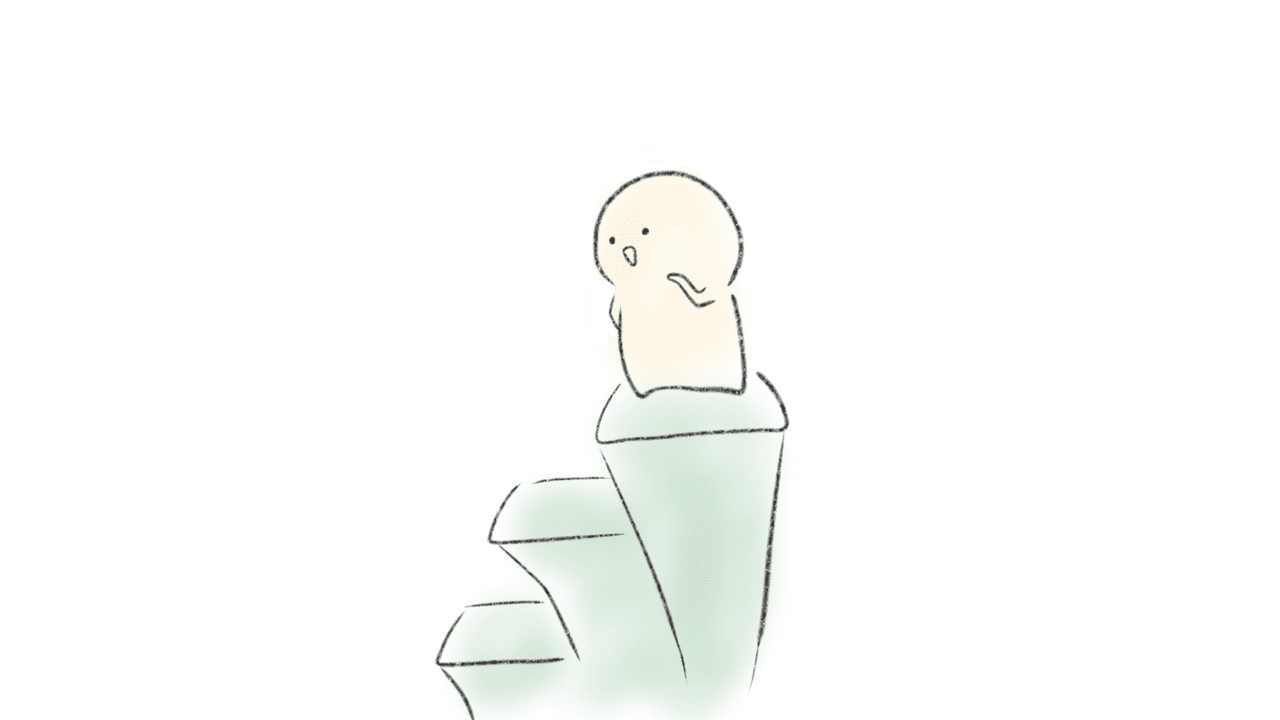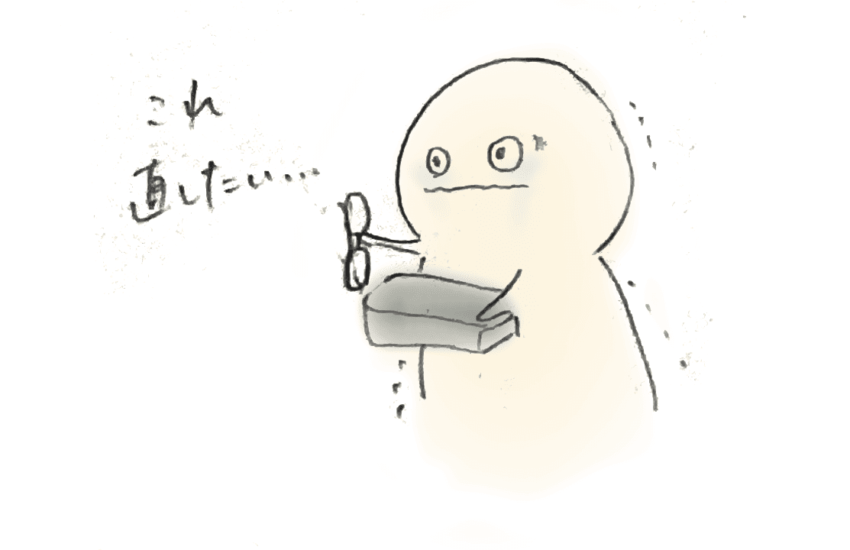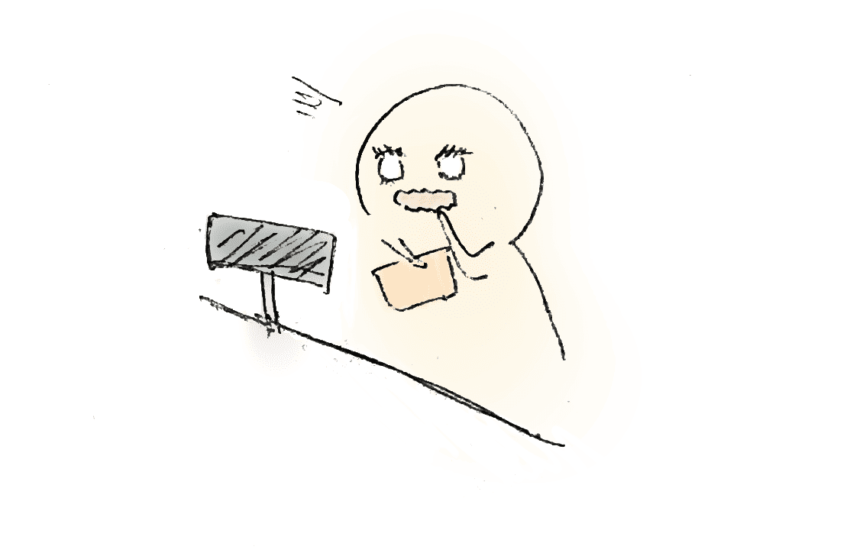ぼんやりでも続けてきたものって、案外ちゃんと積みあがってるのかも
今日は月に2度ほどある書道のお稽古日。なんとなく始めて。もうかれこれ15年ほどになるのかなあ。そんな大したことをやっているつもりはなく、ただ淡々と、細々と続けてきたらいつの間にか今、という感じ。やっぱり、義務教育の開始とともに始めたものだから、常に勉強とか部活とかと並行して取り組んできた。だからこそ、ある程度の距離を保ちつつ付き合ってこられた気がする。教室に所属していた同世代が次第に書道から離れていくなか、なんとなく続けてきた。特に辞める理由がなかったから続けてきた。さすがに受験直前のころは中断しようと思ったけど、気づけば活動を控えただけで、中断はしなかった。一番の難関だと思ってた受験期があっさり終わり、ますます止める理由がなくなったので、続けてたら、なんか今に至るというわけ。まあ翻ると、それくらいの出力でもやってこられたということ。細々とでも続けることができるという点で書道っていいかも。
もっとも、いろいろと時間を持て余していたはずの中学生時代とかに集中して取り組んだり、古典作品を学んだり、臨書してみたりと、積極的に動いていれば、今もっと腕前を上げていたかもしれないね。それは本当に思う。
特にそう感じたのは、「書の甲子園」に出品したときかな。あれだけ真剣に取り組んだことはないってくらいに、集中して、何枚も何枚も書いた。今まで使ったこともなく、縁もないだろうと思っていた全紙に書くことになったから、作業が大変だった。作業部屋の床ギリギリに紙を敷くので、足の踏み場がないような状態。しかも夏。暑い。全紙なんて安くはないから、新聞紙を広げて練習して。いざ本番に臨んでも、うまくいくところがあればうまくいかないところがある。その繰り返し。なかなか、プレッシャーがすごい。真っ白の大きい紙にひと筆を下ろす瞬間、すべてが決まるような気がする。その緊張感を経てようやく出来上がった作品を応募したけど、特に入賞はせず。自分なりに頑張っていい作品ができたと思っただけに、悔しさを覚えた。入賞者の作品を見て、圧倒的な力量の差を感じた。同世代がこんな作品を書いている。筆遣いが違う、空間の取り方が違う。ダイナミックだと思ったら細部は繊細だったり。甘ちゃんだったなと思った。自分は井の中の蛙だと思った。あれから全紙を扱ったことはないけれど、本当にいい経験だったと思う。
自分ではコンスタントに取り組んできたつもりでも、書道に対する心持ちは多少変化s居続けてきた。ぽんぽん進級できるときは、「あれ?なんか意外といけるんじゃね?」とか調子乗りやがる小娘。で、ちょっと伸び悩み始めると途端に必死になったり、あるいは作品を書くのがちょっと面倒に感じてしまって、精彩を欠くものばかりが出来上がったり。いろいろ。
私の師匠は優しい方なので、私の筆の調子がぐらぐらしているときでもあまり厳しいことは言わず、やんわりと、でもしっかりと導いてくださる。厳しく言われるのが大嫌いだった小学生の私には、最高の先生だった。あの方だったからこそ、私も今まで書道を続けてこられたんだと思う。
よく言えば勉強と並行して、悪く言えば勉強の片手間に続けてきたような書道だけれど、15年も続けているとそれなりに積みあがってくるものがあるらしい。積み立てNISAみたいに。ちょこちょこ賞をいただけたし、自分の作品で掛け軸も作れたし、高名な先生方の指導を受ける機会や、新しい展覧会に出品する機会にも恵まれた。うん。わりと、歩んできた道は総じて悪くない。
積み上げてるときには気づかないけど、振り返ってみたら、案外積みあがっているもんなんやなー。